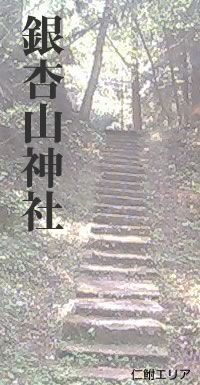銀杏山神社
|
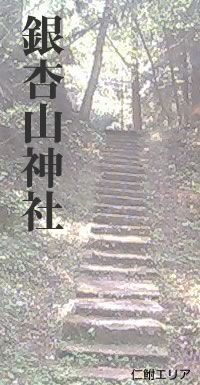 |
大和朝廷時代(658年)、阿部比羅夫が蝦夷征伐に遠征して来た際に、勝利祈願の為に建立したものといわれ、1300年以上の歴史を誇る。
境内にある3本の銀杏の木は、この時に種が植えられたものと伝えられ、樹高25メートル、根回り9メートルの巨木で、昭和30年1月に秋田県天然記念物の指定を受けている。
3本のうちの女いちょうと呼ばれる木は、幹の一部が乳房のように垂れ下がっていて、昔からお乳の出ない女性が願をかけたと言われる。
江戸時代、佐竹の奥方様も願かけに詣でたところこれが叶い、この神社は佐竹家の家紋をつける事を許されたと言われる。
また、手をつないだように太い枝でつながった二本の銀杏の間を一気に3回、8の字に回ると良縁がかなうと伝えられている。
沢を挟んで2株が対峙しており、対岸の一本は2本が癒着した合体木であるが、なかなかの大きさである。
神社から奥の沢にかけては、普段は人が来ない静かな別天地のようなところ。 |
|
 |
林の中の参道への入り口、大鳥居。 |
|
林の参道を抜けると、光あふれる境内が現れます。 |
 |
|
 |